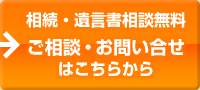遺留分とは
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 (民法1028条)
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
遺留分とは、法律が最低限保証している相続人の取り分です。
相続が発生すると、相続財産は法定相続分どおりに分配されるか、もしくは相続人間で遺産分割協議をしてそのとおりに分配されることになり、この場合は、相続人主導で財産分けをすることになります。
しかし、被相続人は遺言書を残すことで、自分主導の相続財産の分配をすることが可能となります。
例えば「妻に全財産を相続させる」とか、「土地建物の不動産は長男に相続させ、預貯金関係は二男に、株券は妻に相続させる」など、法律の趣旨にはずれなければ、かなり自由な取り決めをすることができます。
ところが、遺言書の内容によっては、相続人であるのに相続できなくなる人がでてきます。(前述の「妻に全財産を相続させる」といった場合、子供たちは相続人なのに相続する財産が無くなります。)それはかわいそうだということで、遺留分の制度が存在するのです。
また、遺留分があるのは、相続人の中でも「配偶者」「直系卑属(子供や代襲相続の場合の孫等)」「直系尊属(親等)」だけで、「兄弟姉妹」には遺留分がないので注意してください。
自分の相続人が配偶者と兄弟姉妹だけという場合、「配偶者にだけ相続させて、兄弟姉妹には相続させたくない」というときは、「配偶者に全財産を相続させる」といった遺言書をつくっておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、法律上何の問題もなく配偶者が財産を取得することが可能になります。
遺留分の計算例その1 相続財産が1000万円 相続人は配偶者と子供が2人
- 配偶者の遺留分は 1000万円×2分の1×2分の1=250万円
- 子供1人の遺留分は 1000万円×2分の1×2分の1×2分の1=125万円
遺留分の計算例その2 相続財産が1000万円 相続人は配偶者と親が1人
- 配偶者の遺留分は 1000万円×2分の1×3分の2=333万円
- 親の遺留分は 1000万円×2分の1×3分の1=166万円
遺留分の計算例その3 相続財産が1000万円 相続人は親が2人
- 親1人の遺留分は 1000万円×2分の1×3分の1=166万円
遺留分も放棄できる
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 (民法1043条)
遺留分の放棄は相続放棄と異なり、相続開始前でも相続開始後でもどちらでもできますが(相続放棄は相続開始後に限られる)、相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要となります。
また、遺留分の放棄は「あくまで遺留分を主張しない」というだけであり、遺留分を放棄した後でも相続人であることには何ら変わりはありません。(相続放棄の場合、相続放棄をした相続人は相続人の地位を失ってしまいます。)
そのため、ある相続人が遺留分の放棄をしたとしても、その相続人は遺産分割協議や遺言の内容によっては、問題なく相続財産を取得できるのです。
相続開始前に遺留分の放棄が認められるには、
- 遺留分の放棄をすることにつき正当な理由がある。
- 本人の意思に基づくものである。
- 遺留分の放棄をする代わりに相応の対価をもらっている。
等の要件がありますが、これらの要件をすべて満たしている必要はありませんので、一応の目安にしてください。
ちなみに、それぞれの要件を細かく見ていくと、1の正当な理由については、被相続人が農業や事業をしていて、それを息子一人に継がせたいときなどです。
2については、他人に強制されて遺留分の放棄をしていないことの確認のため。
3は、遺留分の放棄は将来得るであろう相続財産を放棄するに等しい行為ですから、事前にそれ相応の対価をもらっていれば、遺留分の放棄も納得できるということです。
相続開始前に遺留分の放棄をするには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
遺留分の放棄をする人の住所地ではありませんから気を付けてください。
申立には800円分の収入印紙と予納切手、それから財産目録も必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所で事前に確認してください。
しかし、相続開始後に遺留分を放棄するには特段の手続きは必要ありません。一筆書けばいいだけです。
「私は被相続人○○の相続財産に関しては遺留分を放棄します。」と。
また、遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分が増えるわけではありませんのでここも注意してください。
遺留分減殺請求権
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することが出来る。 (民法1031条)
先に述べたように、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められますが、遺言内容によっては遺留分を侵害されることがあります。(「全財産を妻に相続させる」といった遺言があれば、子供の遺留分が侵害されます。)
遺留分の侵害とは、自分の遺留分相当額の相続財産がもらえない状態のことです。
その場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人、受遺者、受贈者に対して遺留分減殺請求という権利を行使することができます。
自分の遺留分が500万円として、しかし実際に相続できる金額が300万円だとすると、残り200万円について遺留分減殺請求権を行使することが可能です。
しかし、ここで問題なのが次の点です。
- 遺留分としての割合は何を基礎として計算するのか?
- 誰に遺留分減殺請求権を行使するのか?
- 遺留分減殺請求権はいつまでにしないといけないのか?
遺留分の計算根拠
遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 (民法1029条)
相続開始時(被相続人が死亡したとき)に、相続財産が1000万円あったとします。
しかし、生前1000万円を知人に贈与していたとすると、1000万円(相続開始時の財産)+1000万円(生前贈与していた財産)=2000万円を遺留分算定の基礎となる財産として計算していきます。
それでは、一ヶ月前に贈与した場合と10年前に贈与していた場合とでは違いはないのでしょうか?
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、1029条の規程によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。(民法1030条)
原則として、相続開始時を起点としてそこから1年前までにした贈与分については遺留分算定の基礎となる財産になります。
1年以上前にした贈与については、遺留分算定の基礎となる財産にはなりません。
しかし、贈与した人(被相続人)と贈与を受けた人双方が、その贈与により遺留分権利者の遺留分を侵害するとわかっていながら贈与をした場合は、相続開始時から1年以上前の贈与であっても遺留分算定の基礎となる財産になります。
また、贈与を受けた人が相続人である場合は、原則として、いつ贈与したかに関係なく遺留分算定の基礎となる財産とします。
903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、本条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
(最判平10・3・24民集52-2-433)
自分が遺留分としていくらもらえるのか計算するときは、被相続人が生前に贈与したものがないか、また相続人が特別受益をうけていないか、そこを確認しないと正確な数字は出てきませんので注意して下さい。
誰に遺留分減殺請求権を行使するのか?
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 (民法1031条)
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 (民法1033条)
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。 (民法1034条)
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。 (民法1035条)
遺留分減殺請求権は、遺贈と贈与があれば遺贈を受けた人(受遺者)にまずはします。
受遺者が数人いれば、それぞれの目的価額の割合に応じてしていきます。
それでもまだ遺留分を侵害している場合にのみ、次は贈与を受けた人に対して権利行使します。
この場合は、遺贈と違い後の贈与から順にさかのぼる形で権利を行使していきます。
【具体例】
◆例1 遺留分侵害額が600万円 A,B,Cがそれぞれ900万、600万、300万の遺贈を受けた場合
1034条により、Aに300万、Bに200万、Cに100万ずつの遺留分減殺請求権を行使することができます。(Aだけに600万円請求することはできません。)
◆例2 遺留分侵害額が500万円 相続開始1ヶ月前にAに200万円、3ヶ月前にBに500万円の贈与があった場合
1035条により Aに200万円、Bに300万円ずつの遺留分減殺請求権を行使することができます。
遺留分減殺請求権はいつまでに行使しないといけないのか?
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。 (民法1042条)
遺留分減殺請求権は、
- 被相続人が亡くなったこと
- 生前に遺留分を侵害するような贈与がされていたこともしくは、遺言書が発見されそこに遺留分を侵害するような遺贈があったこと
この双方を知ったときから1年又は相続開始から10年、どちらか早い方の時の経過により、その権利行使ができなくなります。
遺留分減殺請求権の行使の方法は特に決まってはいませんが、実務上は内容証明郵便で権利行使の旨を伝えます。